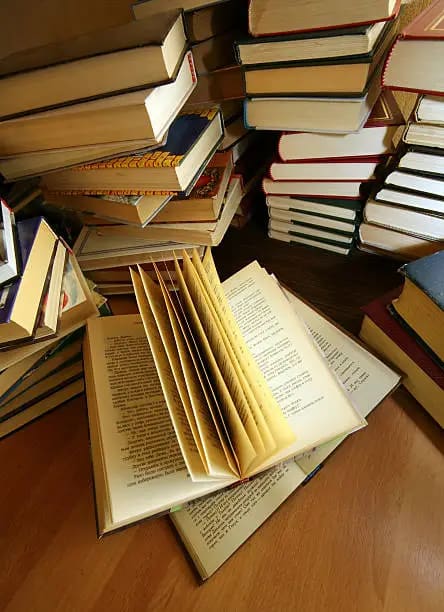
Gerontology Research Group
「生きる」を、問う。
人口増加が著しい現代において、国際社会は食糧安全保障や医療インフラの未発達といった大きな課題に直面しています。そんな現代において重要なのが、すべての人にとって生きやすい「社会インフラストラクチャの設計」です。
ジェロントロジーは「個(個人のエイジング:加齢)」と「地域社会」の両面から諸問題の解決に取り組む学問領域。私たちは、ジェロントロジーの知見を活かした地域包括ケアシステムの構築を模索しています。
あなたにとって「生きる」とは。
生きるとは、ただ息をすることにとどまりません。過去に受け継いだ願いを、未来へと渡すこと。
歩みを止めずに、今日という一日を積み重ねること。最後の瞬間まで、自分らしく燃え尽きること。
それは、「私は確かにここにいた」と未来に残せる何かを刻むことではないでしょうか。
永野ゼミナール
ジェロントロジー研究班
プロジェクト概要
| プログラム責任者 | 永野 聡(立命館大学産業社会学部・教授) |
| ターゲット | この世に生きる全ての人、後世まで生き続けたいと考えている人 |
| 内容 | ACPツールキットの開発を通じた、急激な少子高齢化・人口減少に伴う社会課題(医療崩壊、多死社会など)の解決。Tele Absenceの実証的研究 |
| 目的・ゴール | ○結果を医療従事者と共有し、より良い医療現場の創出を実現する ○人生の中での経験と最後の希望との関係を明らかにすることで、どのような要因が希望に関係しているかということへの理解を深め、論文として発表することで社会に貢献する |
| 共同研究 | MIT Age Lab |
本研究室の担当研究者
Ben Waber
MIT Media Lab 客員研究員 / (一社)ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会名誉理事 ほか
メッセージ
あああ

ACPツールキットの開発目的
- 「人生の最終段階における意思決定」を考えるきっかけを創出すること
- 「人生の最終段階における意思決定」にまつわる情報をACPと共有すること
- 生きた証を、記憶として後世へ残すこと
研究方法
【基礎】ACPツールキットの開発と検証
▶︎被験者(高齢者限らず)の「人生の最終段階における意思」抽出
【展開】「高齢社会」に向けた社会インフラストラクチャの設計
▶︎抽出した情報のACPへの還元
【応用】“意思の痕跡”を集め、記録し、再現する
▶︎主人公の意思やメッセージなど「生きた証」を抽出し保存、記録する。record
▶︎保存された記録から「意思の痕跡」を再現し、幻想的なコミュニケーションチャンネルによって「不在の存在」を構築する。remember
なぜ今、私たちはこのテーマに取り組むのか? –What We Do
現代の日本社会において、急激な少子高齢化と人口減少はさまざまな社会課題を誘発しています。日本の倍加年数(少子高齢化の速度)は、欧米と比較して異例の速さで進むと同時に、日本の人口減少*も著しい一方で、平均寿命は延伸傾向にあり2065年(42年後)には現役世代 1.3 人で 1 人の 65 歳以上の者を支える社会が予測されています。
*総人口が一億二千万人だった2023年から、2065年(42年後)には9,000 万人を割り込む見込み
そうした未来を前に、自分が受けたい医療やケアについて元気なうちから本人主体で家族や医療・介護の専門家と話し合い、意思決定をしておく「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」の必要性が高まっています。ACPの実現には、本人が今後の人生や生きがいを考え、周囲と共有することが重要です。しかし、高齢者自身がそれを言葉にするのが難しい、医療者が多忙でコミュニケーションが不足しがちである、といった課題があります。実際に、厚生労働省の調査では国民の約7割が「人生の最期について話し合ったことがない」と回答しており、その最大の理由は「話し合うきっかけがなかったから」です。このような課題を解決するため、高齢者の方が楽しみながら自らの人生を振り返り、将来について考える機会を作ることを目指し、「60歳からの人生ゲーム」を開発し、それを用いたワークショップを実施しています。
また、ChatGPTに代表される生成AIが加速度的に発達し、日常生活においても様々なシーンで運用されてきています。昨今、AIを用いて人間を再現する取組みも実施されています。しかし、AIには再現できない人間の未知なる領域・力量があるのではないかと私たちは考えており、Tele Absence研究では人間の「記憶」に着目しています。
私たちが描く未来
「60歳からの人生ゲーム」を活用した研究では、高齢者の生きがい創出を目指しています。高齢化が急速に進行する現代では、年金制度、医療制度、高齢者ケアなどの分野で新たなニーズが発生しています。高齢者の生活満足度や健康状態の向上も重要な指標の一つだといえ、高齢者の生きがい創出は非常に重要だと捉えています。また、逼迫する地域医療と連携し、より良い地域包括ケアシステムの構築も目指しています。
Tele Absence研究では、人間とは何かの本質に迫ることを目的としています。それと同時に、忘れられることへの不安、不在となることへの不安へ向き合い、その不安から少しでも解放されるように人の記憶を残すことを目的としています。これらの経て、AIとの比較研究を行うことにより人間の本質に迫ります。
私たちのアプローチ –How We Work
60歳からの人生ゲーム:
高齢者を対象にワークショップを全国各地で実施しています。過去2回バンクーバーでも実施し、その規模を世界にまで広げることに挑戦中です。
コンテンツの商品化に向けてもプロジェクトを進める予定です。
テレアブセンス研究:
三重県志摩市の志摩市民病院を舞台に、臨床実習生の実習に密着したドキュメンタリーを制作しました。江角医師から実習生に向けた想いの伝わり方を研究。企画・撮影から編集までゼミ生で実施し、ナレーション収録も終えました。完成まであと一歩です。
江角医師の想いをAIを介して実習生に伝える研究にも挑戦中です。
江角先生へのインタビューや、過去の取材記事を読み込んだAIを作成し、本人に代わって実習生に想いを伝えることができるのか?という仮説の元、研究を進めています。
今後はドキュメンタリーとAI用いた、差分研究を実施し、分析する予定です。
これまでの活動と成果 –What We've Done
60歳からの人生ゲーム:
先代から作成と改良を繰り返してきたこのツールは、過去に学会での発表やグッドデザイン賞を受賞するなど、様々な場面で高く評価をされてきました。また、実用性と汎用性を兼ね備えたツールとして、国内外でワークショップを継続的に実施しています。
テレアブセンス研究:
三重県志摩市の志摩市民病院で1カ月間臨床実習生に密着し、ドキュメンタリーとして20分弱×2本の映像を制作。江角医師から指導を受けながら、日を追うごとに成長する実習生の姿をカメラに収めました。構成・撮影・編集まで学生で行い、三宅民夫アナウンサーにナレーションを務めていただきました。
これからの挑戦 -What's Next
進行する高齢化社会、よりよく生きるには?
私たちはこれまでに高齢者とのワークショップを通じて、高齢者の本音を聞き出す活動を行ってきました。また、残したい思いや気持ちをどうすれば後の世代につないでいくことが出来るのかにも注目をして活動を行っています。
高齢化が進行する今の社会でよりよく生きるために自分達が何が出来るのかを一緒に考えて行きませんか?
文責:ジェロントロジー研究班7期生
